京都大学 学部別入試情報と科目別傾向と対策 2025年(2024年度)

年度別
京都大学 学部別 偏差値(目安)
| 学部 | 偏差値 (目安) | 備考 |
| 医学部 | 72.5 (医学科) | ※医学科は最難関 |
| 60.0 (人間健康科学科) | ||
| 文学部 | 67.5 | |
| 法学部 | 67.5 | |
| 教育学部 | 65.0 – 67.5 | (文系・理系含む) |
| 経済学部 | 65.0 – 67.5 | (文系・理系含む) |
| 総合人間学部 | 65.0 – 67.5 | (文系・理系含む) |
| 理学部 | 65.0 | |
| 薬学部 | 65.0 | |
| 工学部 | 62.5 – 65.0 | (学科により異なる) |
| 農学部 | 62.5 – 65.0 | (学科により異なる) |
2024年度(前期日程)のおよその実質倍率
2024年度一般選抜(前期日程)における実質倍率(受験者数÷合格者数)の目安です。
| 学部 | 2024年度 実質倍率 (目安) |
| 総合人間学部 | 約 3.5倍 (文系: 3.5倍, 理系: 3.5倍) |
| 文学部 | 約 3.0倍 |
| 教育学部 | 約 3.6倍 (文系: 3.7倍, 理系: 3.2倍) |
| 法学部 | 約 2.6倍 |
| 経済学部 | 約 3.4倍 (文系: 3.2倍, 理系: 4.9倍) |
| 理学部 | 約 2.7倍 |
| 医学部 (医学科) | 約 2.7倍 |
| 医学部 (人間健康科学科) | 約 3.4倍 |
| 薬学部 | 約 2.6倍 |
| 工学部 | 約 3.0倍 |
| 農学部 | 約 2.8倍 |
(注)倍率は過去の実績であり、年度によって変動します。
📚 学部別 入試科目(前期日程)
京大は、阪大と異なり、多くの学部で共通テストの配点を圧縮(あるいは合否判定にのみ使用)し、二次試験の得点を最重視する傾向が極めて強いです。(例:医学部医学科は共通テストが「第一段階選抜」にのみ使われます)
共通テスト(2025年度入試 ※情報Iが追加)
- 文系学部 (文・教育(文)・法・経済(文)・総合人間(文))
- 国語
- 地歴・公民 (「地総/地理探究」「歴総/日本史探究」「歴総/世界史探究」「公共/倫理」「公共/政経」から2科目)
- 数学 (数IA, 数IIBC)
- 理科 (「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目、または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目)
- 外国語 (英語 ※リスニング含む)
- 情報 (情報I)
- 理系学部 (理・医・薬・工・農・総合人間(理)・教育(理)・経済(理))
- 国語
- 地歴・公民 (上記文系と共通の5区分から1科目)
- 数学 (数IA, 数IIBC)
- 理科 (「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 ※学部学科により指定あり)
- 外国語 (英語 ※リスニング含む)
- 情報 (情報I)
二次試験(個別学力検査)
- 文系 (文・教育(文)・法・総合人間(文))
- 国語 (現代文, 古文)
- 数学 (文系数学)
- 外国語 (英語)
- 地歴 (世界史探究, 日本史探究, 地理探究 から1科目)
- 経済学部 (文系)
- 国語 (現代文, 古文)
- 数学 (文系数学)
- 外国語 (英語)
- ※経済学部(文系)は、上記3科目に地歴を加えたAタイプと、地歴を課さず数学の配点が非常に高いBタイプのいずれかで合否判定されます。
- 理系 (理・医・薬・工・農・総合人間(理)・教育(理)・経済(理))
- 国語 (現代文, 古文)
- 数学 (理系数学)
- 外国語 (英語)
- 理科 (物理, 化学, 生物, 地学から2科目 ※学部学科により指定あり)
- 面接 (※医学部医学科、人間健康科学科の一部専攻のみ)
📝 主要科目の傾向と対策(二次試験)
京大の二次試験は、全教科で「思考のプロセス」を深く問う良問が出題されます。
英語 (120分)
- 傾向
- 大問は長文読解2題、和文英訳1題の構成が基本です。(年度により自由英作文も)
- 試験時間(120分)には比較的余裕があります。
- **「英文和訳」と「和文英訳」**の比重が非常に重いのが特徴です。
- 長文は、抽象的・哲学的な内容(科学論、文化論など)が多く、文脈を深く理解した上での高精度な和訳が求められます(下線部和訳)。
- 和文英訳は、一見すると平易な日本語ですが、その裏にあるニュアンスや文脈を汲み取り、自然かつ正確な英語に「翻訳」する能力が問われます。
- 対策
- 精読力: 構文解釈系の参考書(『ポレポレ』『英文解釈の技術100』など)を完璧にし、あらゆる英文の構造を正確に把握できる力を養います。
- 和文英訳: 京大対策の最重要ポイントです。 例文暗記(『ドラゴン・イングリッシュ』など)で型を学びつつ、必ず学校や塾の先生に**「添削」**を受けてください。日本語の逐語訳ではなく、「意訳」する勇気と技術が必要です。
- 語彙: 難易度の高い単語帳(『鉄壁』『ターゲット1900』の上級レベル)は必須です。
数学(理系) (150分・大問6題)
- 傾向
- 微積分(数III)、確率、整数、空間図形が頻出です。
- 難易度は国内最難関レベル。「解法暗記」は一切通用しません。
- 問題設定はシンプルに見えても、深い思考と数学的センス(発想力)を要求する、いわゆる「パズル的」な良問が多いのが特徴です。
- 高い計算力はもちろん、自分の解法が正しいことを示す**「論証力」**が厳しく問われます。
- 対策
- 本質的理解: 教科書の定義や定理を「なぜそうなるのか」説明できるレベルまで深く理解します。
- 思考訓練: 網羅系参考書(青チャートなど)の例題を完璧にした後、すぐに過去問に入るのではなく、思考力を鍛える標準〜発展的な問題集(『スタンダード演習』など)で「考え抜く」訓練を積みます。
- 過去問演習: 京大の過去問(「赤本」や、解説の詳しい「黄色本」など)を徹底的に研究します。解けなかった問題は、解答を見て理解した後、必ず自力で答案を再現できるようにしてください。
- 論証: 答案は「数学的な作文」です。論理の飛躍がないか、常に添削指導を受けることが望ましいです。
数学(文系) (120分・大問5題)
- 傾向
- 確率、整数、微積分(数II)、図形と方程式が頻出です。
- 理系同様、「解法暗記」が通用しない思考力・発想力を問う問題が出題されます。文系数学としては国内最難関です。
- 論証力が問われる問題も多いです。
- 対策
- 基礎の徹底: 理系と同様、教科書レベルの定義や原理を深く理解することがスタート地点です。
- 標準問題の習熟: 青チャートなどの例題を「解法を説明できる」レベルまでやり込みます。
- 過去問: 京大の文系数学は独特の「ひらめき」を要する問題が多いため、過去問演習を通じて京大の「クセ」に慣れることが不可欠です。
国語 (文系120分, 理系90分)
- 傾向
- 阪大や東大と異なり、「漢文」は出題されません。 現代文2題、古文1題の構成です。
- すべてが記述式問題であり、解答欄が非常に広い(=まとめる力が必要)のが特徴です。
- 現代文 (文理共通)
- 抽象度の高い評論(哲学、科学、芸術など)が好まれます。
- 設問は「〜とはどういうことか、説明せよ」という形式が中心。傍線部の単なる言い換えではなく、本文全体の論理展開を踏まえて、筆者の主張の核心を自分の言葉で再構成する能力が求められます。
- 古文 (文理共通)
- 標準〜やや難レベル。文法(特に助動詞、敬語)や単語の基礎知識を前提に、主語を正確に補い、文脈を精密に読解する力が問われます。和歌の解釈も頻出です。
- 対策
- 現代文: 過去問や東大の現代文など、骨太な評論を読み解く訓練を積みます。「解答の要素を本文から抜き出し、設問の要求に合わせて論理的に並べ替える」練習を徹底し、必ず添削を受けてください。
- 古文: 文法と単語を完璧に暗記した後、主語や目的語を補いながら正確に現代語訳する訓練を積みます。
理科(物理・化学) (理科2科目で180分)
- 物理
- 傾向: 大問3題(力学、電磁気はほぼ必須。残りが熱力学 or 波動)。
- **「問題文が長く、設定が複雑」**なのが京大物理の最大の特徴です。初見の状況や、大学物理の初歩的な内容を背景にした問題も出されます。
- 公式を暗記して当てはめるだけでは解けません。「物理法則の根本的な理解」(なぜその法則が成り立つのか)を問う問題が多いです。
- 対策: 参考書(『名問の森』など)で標準問題を解けるようにした後、過去問演習で「長い問題文を読み解き、状況をモデル化する」訓練を徹底します。計算力も重要です。
- 化学
- 傾向: 理論化学、有機化学(特に構造決定)が中心で、無機化学の出題は少なめです。
- **「有機化学の構造決定」**は京大化学の代名詞であり、非常に難易度が高いパズル的な問題が出題されます。
- 理論化学も、単なる計算問題ではなく、化学平衡や反応速度の本質的な理解を問う問題や、初見の題材を扱った考察問題が多いです。
- 対策: 理論化学(平衡、反応速度、熱化学)は原理から深く理解します。有機化学は、知識の暗記に加え、過去問や専用の問題集で「構造決定の思考プロセス」を徹底的に訓練します。
文学部
- 配点(合計 750点)
- 共通テスト:250点(1000点満点を圧縮)
- 二次試験:500点(国語150, 地歴100, 数学100, 英語150)
- 特徴
- 京大の文系学部の中で、二次試験の国語と地歴の配点比率がやや高いのが特徴です。
- 二次試験の地歴は「日本史探究」「世界史探究」「地理探究」から1科目選択します。
🏛️ 法学部
- 配点(合計 885点 ※2025年度から変更あり)
- 共通テスト:285点(1000点満点を圧縮)
- 二次試験:600点(国語150, 地歴100, 数学150, 英語200)
- 特徴
- 2025年度入試から、二次試験の英語が150点→200点満点に変更され、重要度がさらに増しました。
- 二次試験の地歴は「日本史探究」「世界史探究」「地理探究」から1科目選択します。
🏛️ 経済学部
経済学部は、文系と理系で入試が分かれており、特に文系は出願時に2つのタイプを選択します。
経済学部(文系)
- Aタイプ(地歴選択型)
- 共通テスト:225点(1000点満点を圧縮)
- 二次試験:550点(国語150, 地歴100, 数学150, 英語150)
- 特徴: バランス型。地歴(日本史/世界史/地理)を受験します。
- Bタイプ(数学重視型)
- 共通テスト:225点(1000点満点を圧縮)
- 二次試験:550点(国語150, 数学250, 英語150)
- 特徴: 二次試験で地歴を課さず、その代わりに数学の配点が極めて高いタイプです。数学が得意な受験生向けの方式です。
経済学部(理系)
- 配点(合計 875点)
- 共通テスト:225点(1000点満点を圧縮)
- 二次試験:650点(国語100, 数学250, 理科150, 英語150)
- 特徴
- 二次試験で数学の配点が250点と、理系科目(理科は150点)より重視されています。
- 二次試験の理科は「物理」「化学」「生物」から1科目を選択します。
🔬 理学部
- 配点(合計 1050点)
- 共通テスト:250点(1000点満点を圧縮)
- 二次試験:800点(国語100, 数学250, 理科300, 英語150)
- 特徴
- 二次試験の配点が800点と非常に高く、特に**理科(2科目で300点)と数学(250点)**の比重が極めて高い、典型的な二次試験重視・理系科目重視の配点です。
- 二次試験の理科は「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目を選択します(地学を選択できるのが特徴です)。
🔬 工学部
【2025年度 最も大きな変更点】 工学部は、2025年度入試から共通テストの「数学」「理科」「情報」も最終的な合否判定の得点に加算されるようになります。
- 配点(合計 950点)
- 共通テスト:250点(国・地公・英・情・数・理の合計)
- 二次試験:700点(国語100, 数学250, 理科200, 英語150)
- 配点の詳細
- 共通テスト(250点満点):
- 「国語」「地歴・公民」「外国語」「情報I」の成績を150点満点に圧縮。
- 「数学(I・AとII・B・C)」の成績を50点満点に換算。
- 「理科(2科目)」の成績を50点満点に換算。
- これらを合計して250点満点とします。
- 二次試験(700点満点):
- 理科は「物理」と「化学」が必須です。(地球工学科・工業化学科の一部を除く)
- 共通テスト(250点満点):
- 特徴
- 従来は共通テストの数学・理科は足切りにしか使われませんでしたが、2025年度からはすべての共通テスト科目が最終得点に入ります。
- 二次試験の配点(700点)の比重が依然として高いですが、共通テスト対策もより重要になりました。
🏥 医学部
医学部(医学科)
- 配点(二次試験 + 面接)
- 共通テスト:第一段階選抜(足切り)にのみ使用。(1000点満点中700点程度が例年の目安)
- 二次試験:1050点(国語150, 数学350, 理科300, 英語250)
- 面接:段階評価(A〜C)
- 特徴
- 共通テストは合否の得点には加算されません(足切りラインを超えることが必須)。
- 二次試験の**数学(350点)**の配点が極めて高く、次いで理科(300点)、英語(250点)と続きます。国語も150点と低くはありません。
- 二次試験の理科は「物理」「化学」「生物」から2科目を選択します。
医学部(人間健康科学科)
- 配点(合計 1000点)
- 共通テスト:300点(1000点満点を圧縮)
- 二次試験:700点(理科300, 英語200, 数学 or 国語 200)
- 特徴
- 二次試験は「理科(2科目)」「英語」が必須です。
- **「数学(理系)」と「国語(理系)」**のうち、高得点の方が合否判定に採用されます。
- 理科は「物理」「化学」「生物」から2科目選択です。
💊 薬学部・🌾 農学部・🧑🏫 総合人間学部・🎓 教育学部
これらの学部も、それぞれ独自の配点比率(共通テストの圧縮率や、二次試験の科目別配点)を持っています。
- 薬学部: 理学部と似ていますが、二次試験の数学と理科の配点が理学部ほど極端ではありません。
- 農学部: 学科によって理科の選択(生物必須など)が異なる場合があります。
- 総合人間学部・教育学部: 文系型・理系型で試験が分かれており、それぞれ指定された配点で選抜されます。
【結論として】 学部・学科によって、どの科目を重視しているか(配点)が大きく異なります。ご自身の志望学部の最新の配点を「入学者選抜要項」で確認し、最も配点の高い科目を重点的に対策することが合格への鍵となります。
入試情報
入試結果
この大学を受けた人の滑り止め 大学、学部学科ランキング ベスト3
各科目の学部、学科の科目別勉強方法
あわせて読みたい
-
 2026.02.19
2026.02.19テスト投稿
-
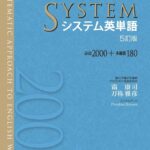 2025.11.14
2025.11.14システム英単語とシステム英単語BASICの違い
-
 2025.11.14
2025.11.14私立大学医学部 偏差値・倍率・学費一覧
-
 2025.11.12
2025.11.12九州大学 2025年 入試科目、倍率、傾向と対策
-
 2025.11.12
2025.11.122025年119回 医師国家試験合格率(2024年118回)私立医学部大学 医師国家試験合格率ランキング
-
 2025.11.11
2025.11.11大阪大学 2024年

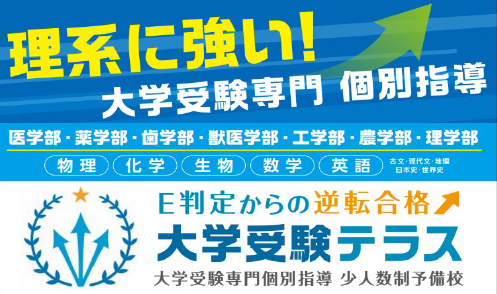



この記事にコメントを送る